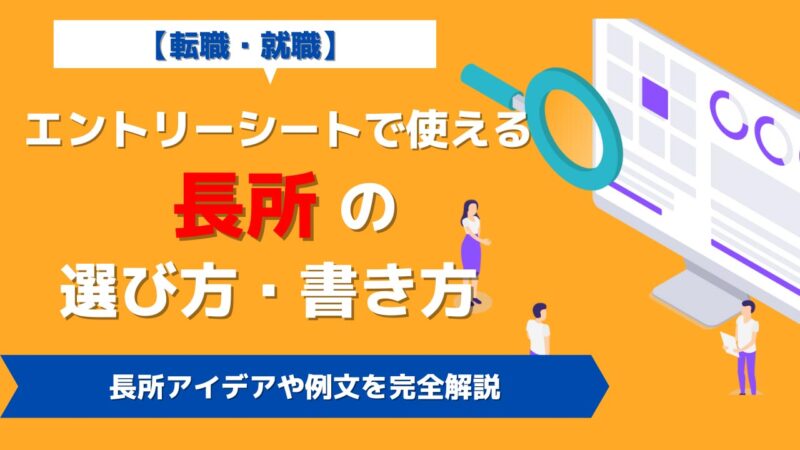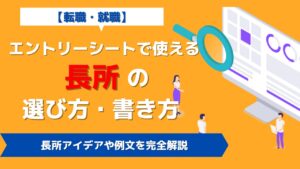転職や就職のエントリーシート(ES)では自らの長所を書くことが多くなります。「人に言える程の長所がないよ」「長所をどう説明すればいいか分からないよ」と悩むことも多いと思います。
長所は大事なアピールポイントですので、しっかり書いて点数を稼ぐ必要がある項目です。ここで採用担当者に刺さる長所を挙げられると書類選考も、その後の面接もペースをつかむことができます。
Twitterで行っている個別相談企画でも長所についての質問は多く、皆さん迷っている部分です。添削を行っている中で気づいたポイントも盛り込んで解説していきます。
この記事では以下の事が分かります。
- 自分の長所が思いつかない方に長所のアイデア
- 自分の過去のエピソードから長所を探し出す方法
- 長所の記入欄で実際にどのように書けばいいかの実例
長所をアピールするのが苦手な方でも書けるように、例文やアイデアを手厚く解説していますので、ぜひご覧ください。
エントリーシートでよく聞かれる他の質問についてもそれぞれ徹底解説していますので、書類選考の通過率を上げたい方はぜひチェックしてみてください!
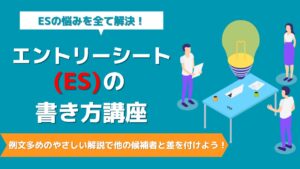
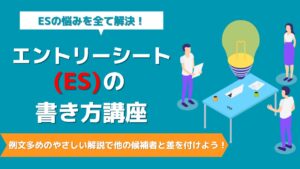
エントリーシート(ES)で使える長所アイデア 長所が思い浮かばない方必見!


「自分の長所が昔から分からない」「自信がなくて長所を挙げられない」こんな方は実は多いです。まずは長所を書くために、どの長所について書くか方向性を決めていきましょう。
長所は主観でOK。他人と比べて劣っていても長所でOK!
エントリーシート(ES)に書く長所は主観で全然OKですので、気軽に「○○が長所です!」と言ってOKです。長所が書けない人の多くは、控えめで思慮深い人が多いです。
「他にもっとすごい人がいるから長所とは言えないかなぁ」と考えていると、なかなか書ける長所がなくなってきてしまいます。自分の中で長所と思えば立派な長所ですので、自信を持って長所といってOKです。
長所は自己PRに繋がるものが使いやすくてベスト!
自己PRに繋がる長所であれば、相乗効果が狙えるのでおすすめです。自己PRと被らないけど、関連のある長所を選ぶことをおすすめします。
- 自己PR いつも明るいこと
-
両親や友人に「私の優れた部分」について聞いたところ、「いつも明るいところ」という意見が多く返ってきます。自分が思っている以上に、いろいろな方が明るさを気に入ってくださっていることを知りました。それ以来、辛いことがあった時や、場の雰囲気が重い時でも私だけはいつも明るく居られるように努めており、今では私のアピールポイントです。
- 長所 初対面でも臆せず話すことが出来ること
-
私の長所は初対面の方にも臆せず話しかけることができることです。大学の講義でのグループワークの際に皆が緊張して話題が進まない中、私は自分から話しかけ議論を活性化することができました。その結果、グループは最優秀賞を取ることができ、「○○さんがグループにいてくれてよかった」という言葉もいただきました。
このようにどちらもコミュニケーション力に関連することであれば、「初対面で臆せず話せる長所を活かして、周囲の方を明るくすることができる」という自己PRに繋げることができるので、相乗効果が高まります。
パクって使える!能力別の長所アイデア
長所が思いつかない方向けに長所のアイデアを例として挙げておきます。「あ、自分でもこの長所なら使えるかも」と思うものが見つかったらぜひ使ってみてください。
コミュニケーション能力に関する長所
- 初対面でも臆せずに話せる
- 場を和ませることができる
- 自分が間に立って、皆をまとめることができる
- 大人数の前でも自信を持って話せる
- 大きな声で話せる
- 相手の立場になって話せる聞き上手
忍耐力系の能力に関する長所
- 何事も粘り強く取り組むことができる
- 困難にぶち当たっても折れずに模索して行動できる
- コツコツと日々努力することができる
- 失敗をしても切り替えて次にチャレンジできる
特定のスキル系の能力に関する長所
- 文章を書くのが得意
- 体力に自信がある
- パソコンの扱いが得意
繰り返しになりますが他人と比較して劣ると思っても、「自分は得意だ!」と思ったならそれは長所と言って大丈夫です。
長所が思いつかない方向け 過去のエピソードから長所を探し出す方法


それでもどうしても長所が思いつかない方向けに、過去のエピソードから長所を探す方法をご紹介します。私がやってみる様子も書きますので、ぜひ一緒にやってみましょう。
①頑張った・褒められた・成功したエピソードを2~3つ思い出してみる
たくさんエピソードを思い出せる方はたくさんあれば尚良いです。なかなか思い出せない方もいらっしゃると思うので、まずは2~3つ思い出してみましょう。
- 思い出し方の例
-
- 辛かった・しんどかったときの事を思い出してみる その時どうやって打開した?
- 親や先生から褒められた時のこと
- 何かの成功談 受験や資格、講義や仕事など
- 私が思い出したこと
-
- 第一志望の大学に落ちた時は辛かったなぁ…でもその後バイト頑張ったっけ
- 高校時代、数学を教えてもらう為に毎朝先生のところに通うのを1年間続けて「よく頑張った」って言われたっけ…
- お客さんからよく「迅速な対応ありがとうございました」って言われるっけ…
②エピソードの中にあるポジティブな要素を抜き出す
| エピソード | ポジティブな要素 |
|---|---|
| 第一志望の大学に落ちた時は辛かったなぁ…でもその後バイト頑張ったっけ | 立ち直った |
| 高校時代、数学を教えてもらう為に毎朝先生のところに通うのを 1年間続けて「よく頑張った」って言われたっけ | 継続した |
| お客さんからよく「迅速な対応ありがとうございました」って言われるっけ | 迅速な対応 |
③今回志望する企業の性格に合いそうなものを主観でいいのでひとつ選ぶ
スピード感のあるベンチャー企業で代表も若い方の会社を受ける→「迅速な対応」を長所にしよう!
先輩インタビューに「しんどいけどやりがいのある仕事」って書いてる。きっとコツコツ頑張る忍耐力が求められる→「継続力」を長所にしよう!
長所は自分の能力の中から、志望企業に合う物を選びましょう
長所をアピールするために注意すべきポイント5選


書けそうな長所が見つかってきたと思います。実際に書いていく前に、長所をアピールする際に注意すべきポイント5選をご紹介します。
具体的な事例を挙げることで長所を証明する
長所をアピールする際には、単に「コミュニケーション能力がある」と書くだけでは説得力に欠けます。具体的な事例を挙げることで、自分がどのような状況でその能力を発揮したのかを説明することが大切です。例えば、「チームメンバーと円滑にコミュニケーションを取り、スムーズにプロジェクトを進めた」というように、自分が過去にどのような業務でコミュニケーション能力を発揮したかを具体的に示すことが重要です。
ポジティブな言葉を使い、自信を持って表現する
エントリーシートは自己アピールの場です。自分自身に対する自信を持って、ポジティブな言葉で表現することが大切です。例えば、「自分自身を信じて、自分の能力を最大限に発揮できる」というような表現をすることで、自信を持った自己アピールができます。
クオリティよりも量よりも、自分の魅力を伝えることに集中する
エントリーシートに書くことは多岐にわたりますが、必ずしも多く書くことが良いわけではありません。重要なのは、自分の魅力を伝えることに集中することです。自分がどのような人物であるか、どのような経験をしてきたか、どのような価値観を持っているかなど、自己紹介をしっかりと行い、自分の強みをアピールすることが大切です。
求められる職種・業界に必要な能力を重視して選ぶ
就職活動において、応募する職種や業界に求められる能力を理解し、自分が持つ能力をアピールすることが非常に重要です。例えば、IT業界では、コミュニケーション能力や問題解決力、新しい技術の習得能力が求められます。一方、営業職では、コミュニケーション能力や交渉力、成果を出す能力が重要視されます。経理職の場合には、数値に強く、正確性や丁寧さ、改善提案力が求められることが多いです。このように、求められる能力は業界や職種によって異なるため、自分がどのような能力を持っているかを理解し、その能力をアピールすることが大切です。
長所と関連する資格・実績を挙げることで、アピールの幅を広げる
応募する職種・業界に合わせた長所を選び、それをアピールすることは非常に重要ですが、それだけでなく、自分が持つ資格や実績もアピールのポイントになります。例えば、IT業界であれば、プログラミング言語の資格を取得していることや、プロジェクトに参加した実績があることがアピールポイントになります。営業職であれば、営業の実績や、営業系の資格を持っていることが重要です。また、人事職であれば、人材採用の経験や、人材育成のための資格を持っていることがアピールポイントになります。
さらに、自分が持つ趣味や特技、社会活動やボランティアなど、それまでの人生で得た経験やスキルをアピールすることも大切です。これらの経験が、応募する職種・業界において必要とされる能力と関連している場合は、積極的にアピールしましょう。
応募する職種・業界に合わせた長所の選び方や書き方


求められる職種・業界に合わせて応募者が持っている能力や経験をアピールすることが、エントリーシートの書き方において非常に重要です。以下では、主要な職種・業界において、求められる能力とアピール方法について紹介します。
IT業界に求められている長所と選び方
IT業界では、コミュニケーション能力、問題解決力、新しい技術の習得能力が重要な能力とされています。特に、プログラマーなど技術職においては、新しい技術に素早く対応し、問題を解決するための能力が求められます。また、チームでの開発作業が多いため、コミュニケーション能力も必要不可欠です。アピール方法としては、開発したシステムやアプリケーションの成果物を提出したり、GitHubなどの開発プラットフォームでの活動履歴を紹介することが有効です。また、関連する資格としては、プログラミング言語の資格やシステム開発の資格を取得しておくと良いでしょう。
営業職に求められている長所と選び方
営業職においては、コミュニケーション能力、交渉力、成果を出す能力が重要とされています。営業職は、顧客とのやりとりが多く、信頼関係を築くことが大切です。また、競合他社との交渉や契約締結の際には、交渉力が必要になります。成果を出す能力については、目標を達成し、売り上げを伸ばすことが求められます。アピール方法としては、過去の営業実績や、顧客とのコミュニケーション履歴を提出することが効果的です。また、営業に関連する資格としては、宅地建物取引士や証券外務員などがあります。
経理職に求められている長所と選び方
経理職においては、数値に強い、正確性・丁寧さ、改善提案力が求められます。数値を扱うため、正確性や丁寧さが必要不可欠です。また、経理プロセスの改善や業務効率化に取り組むこともあるため、改善提案力があるとより一層評価されます。このような長所をアピールする際には、数値に関する知識や経験を持っていることを証明するために、簿記や税理士資格を持っていることや、過去の業績を示すことが有効です。また、経理システムの導入経験や、改善提案を行い実際に業務改善を達成した実績も、アピールする際には重要なポイントとなります。これらの実績を通じて、自分が経理業務に対してどのようなアプローチをしてきたか、また、どのような成果を出してきたかを具体的に示すことで、採用担当者からの評価を高めることができます。
クリエイティブ職に求められている長所と選び方
クリエイティブ職においては、アイデアを出す力、センス・感性、コミュニケーション能力が求められます。アイデアを出す力は、クリエイティブなアイデアを独自に生み出すことができる能力であり、センス・感性は、美的センスや表現力が求められます。また、クリエイティブな業務は、チームでの作業が多いため、コミュニケーション能力も必要です。プレゼンテーション力や共感力なども必要とされます。
人事・採用職に求められている長所と選び方
人事・採用職においては、コミュニケーション能力、分析力、採用面接の経験やスキルが求められます。採用においては、優秀な人材を探し出すために、適切な問いかけや面接のテクニックが必要です。また、応募者の情報を分析し、採用戦略を考えるために、分析力が求められます。採用戦略の策定や採用面接の実施経験がある場合は、その実績をアピールすることで、採用担当者としての実力をアピールすることができます。
エントリーシート(ES)での長所の書き方


エントリーシート(ES)では「長所を200文字以内で説明してください」などの質問文に出会うことがあると思います。そういった時に実際にどのように書けばいいかを解説します。
長所を書く時の構成 結論ファーストが有効
長所に限らずですが、文章を書く時には構成を考えてから書き出しましょう。長所は基本的には短めの文字数が設定されがちですので、結論ファーストで端的にまとめる必要があります。
短い時間または文字数で端的に内容を伝える時に効果的な手法。文頭に結論を持ってくることで「ああ、この人は今からこのことについて話すんだな」と相手が準備することができるので、内容も頭に入りやすくなります。
「結論→エピソード→結果」基本的にこの3段階で書くことが有効です。長所を紹介することよりも、その長所によってどんなメリットがあったかの説明に文字数を割きましょう。
長所を書く時の文章の割合は1:4:5を心がける
長所を書く時に注意すべきなのが「前提の質問に時間をかけすぎない」ことです。分かりやすいように私の場合の200文字長所の例を出してみます。
私は長所は文章を書くのが得意なことです。特に長い文章を早く書くことに関して自信を持っております。元々読書が好きで、幼少の頃から図書館に入り浸って本を読む生活をしていました。大体週に3回は図書館に通っており、その環境が文章を書くことを得意にしてくれました。加えて、高校の頃は読書感想文コンクールへの出品に力を入れており、入賞するまでになりました。この能力を貴社でも活かしたいと考えております。(195文字)
エピソードが多めで「結果」にあたる部分が少し物足りません。「その長所がどう活きると考えているのか」という部分にもっと触れられると、良い長所のアピールになります。
私の長所は文章を書くのが得意なことです。幼少時に週3回図書館に通う習慣があったことや、高校では読書感想文コンクールへの出品に意欲的だったことが寄与しました。現在では後輩に文章添削を行ったり書記として重宝されており、「とてもまとまっていて分かりやすい」と評価をいただけるようになりました。貴社においてもビジネスメール・会議資料・顧客への訴求文などにおいて能力を発揮できると考えております。(193文字)
長所が実際にどのような評価を受けたか、貴社でどのような場面で役立つのかという部分に多く触れています。採用担当者も想像しやすいので「確かにいい長所だ」と思いやすくなります。
長所は自分の中にある!逆を話せば短所にもなる 書いたらエージェントの添削を受ける
このように、長所は自分の中に必ずあります。自分にあるものから企業に合う物を選び出す作業をすればいいので、きっかけさえあれば誰でも長所をアピールすることができます。
また、長所は短所の裏返しと言えます。例えば粘り強い性格は、裏を返せば諦めが悪い性格とも言えます。「私は諦めが悪い短所がありますが、粘り強く取り組めるという長所にもなっています」などと短所を長所に繋げることもできます。短所についても長所と一緒に考えてみると、引き出しがひとつ増えておすすめです!
一緒に短所についても考えてみましょう。今は必要なくても、短所を聞かれる場合も多いので準備しておこう。
【転職・就職】エントリーシート(ES)で使える短所の選び方・書き方
そして、選んだ長所が企業に合っているかどうかを確認するためには、企業のことを良く知るエージェントに添削してもらうのが一番です。もし選んだ長所があまりよくないようであれば、事前に教えてもらえるのでミスすることがなくなります。エージェントにまだ登録していない人はまずひとつ登録して、添削してもらえる体制を整えておきましょう。